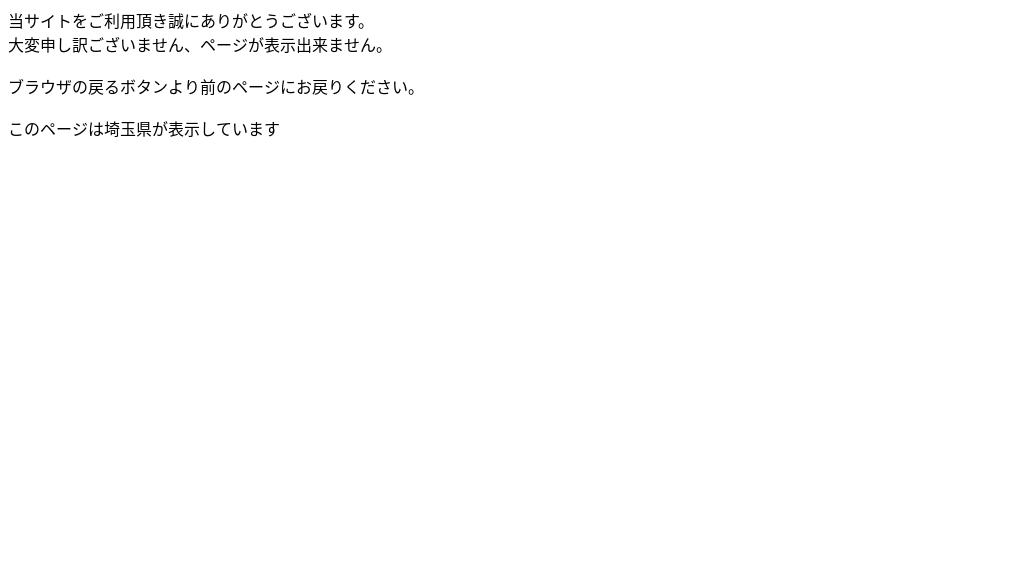全国7万以上の観光・観光地クチコミ検索サイト
全国7万以上の観光・観光地クチコミ検索サイト
境内に1690年(元禄3年)の地蔵道標があり、「これより いかほかいとう」と刻まれている。「いかほかいとう=伊香保街道」のことで、伊香保へ至る途中の渋川で古三国街道が分岐している。この地蔵道標は元々県道392号線沿いにあったもので、伊香保街道とされている道は神流川の方へ向かっており、その道が最初期の中山道。その後に道が付け替えられて、新町に続く中山道が開削された。
歴史あるお寺です。神保原(じんぼはら)駅からはかなり離れているのでバスか自家用車での訪問がおすすめです。武田信玄マニアのかただけでなく、歴史マニア全般におすすめです
曹洞宗崇栄山陽雲寺は、元久2年(1205)の再興と伝えられ、当時は満願寺と号していました。天正10年(1582)、神流川合戦において焼失しましたが、同19年(1591)に、川窪与左衛門尉信俊(武田信玄の甥)によって再建され、居城となりました。
武田氏ゆかりのお寺ということで訪ねてみました。案内板によれば前身の崇栄寺(別の案内板では満願寺)が神流川の戦いで焼出後、金窪村の領主となった武田信玄の甥の川窪信俊が再興、寺号を養母であり信玄夫人である陽雲院の名をとって陽雲寺としたそうです。そうした関係で信玄自筆の起請文、書状などもあるそうです。神流川橋方向から歩いてきたのですが、お寺が見えたので入っていくと、いきなり墓地に入ってしまいました。すぐに目についたのは、武田氏遺臣招魂碑と陽雲院のお墓?です。さらに進むと本堂と鞍間太